俳句エッセー〔7〕 幸せ色の「菜の花」
幸福感をもたらす色なら、映画タイトルになったハンカチをあげるまでもなく黄色。この色から誰もが最初に連想するのは菜の花。新春の九州・指宿に始まり、五月中旬の下北半島・横浜町まで、菜の花前線の北上に合わせて各地で菜の花マラソンが開かれるのは、黄一色の世界を走る心地よさをランナーが知っているからだ。
菜の花はアブラナ科アブラナ属の黄色い花の通称で、白菜、大根、小松菜、野沢菜などの場合も“菜の花”と呼ばれる。文部省唱歌『おぼろ月夜』で「菜の花畠に入日薄れ……」と歌われている奥信濃・飯山の菜の花も野沢菜のものなのだ。千曲川沿いに黄色のファンタジーを繰り広げる花々が信州名産・野沢菜漬にかかわっていると知って、わたしはいっそう親近感を覚えた。
ともあれ、四枚の花弁が十字形に並ぶ菜の花は、蜜蜂ならずとも惹きつけられる愛らしさ。その魅力は遠景にするとさらに増す。ここを大きくとらえた蕪村の句が日本人の心の原風景にまでなっているのも当然であろう。
ところで、江戸中期に六甲山地の摩耶山で詠まれたというこの句の菜の花は、農業研究者からは搾油用だったとされる。菜の花畑はすなわち菜種の畑だったのだ。
そういえば、「野崎村」の場で知られる鶴屋南北の歌舞伎『お染久松色読販(ルビ=おそめひさまつうきなのみようり)』のヒロイン・お染は油屋の娘と言う設定で、恋人・久松を追って駆けつけた野崎村の舞台下手は菜の花のセットと決まっている。油屋の娘にふさわしい道具立てとして、南北が菜の花を指定したのなら、さすがである。
江戸時代は、油といえば一にも二にも菜種油で、灯火にも食用にも用いられ、油粕は畑の肥料になった。菜の花は実利をともなう景観作物といった存在だった。現代、滋賀県東近江市から始まり、日本中に広まった「菜の花プロジェクト」という菜の花を切り口にして資源循環社会を目指す運動がある。眺めて美しく、種子からは油がとれ、廃油は石鹸になり、バイオ燃料として車まで動かせる菜の花パワーに着目したものだが、この祖型はすでに江戸時代からあったのだ。
菜種油に話をもどすと、平成の食卓で植物油といえばサラダ油やオリーブ油が主流だが、じつは知らないうちにわたしたちは菜種油を口にしている。豆腐屋の油揚げや鹿児島名産の薩摩揚げである。からりと香ばしく、骨太のうまみをもった味に揚げるには菜種油がいちばんなのだ。
こんな根強い需要や、前述の菜の花プロジェクト運動の広がりもあって、輸入菜種一辺倒から近年は国産菜種が少しずつよみがえってきて、地油(上2文字に傍点)を謳う生産者も現われているからうれしい。
もちろん、花菜、菜花などの名で食用としても出荷されている。辛子和えや白和えによく、吸い物、蒸し物、鍋の彩りにもぴったり。春を告げるほろりとした辛味、やさしい歯ごたえ、爽やかな緑色と風情満点なうえ、たんぱく質、カロチン、ビタミン、ミネラルが豊富で、蕾にはストレス緩和、精神安定に効くホルモンまであるそうだから、たくさん食べるにこしたことはない。そうそう、菜の花の蕾が注目されたきっかけは京都の菜の花漬だったそうだから、京都の漬けもの屋には先取りセンスがあるといえる。
一方、関東では房総半島の海辺が食用菜の花の特産地。温暖な安房では昔から切り花用に栽培されていたし、養蜂用にもつくられていたので、スムースに食用に転換できたのだ。
わたしは、房総の突端にある白浜町に菜の花を求めて旅したことがある。なのに、探せども探せども一面緑の菜の花畑ばかり。農家の老夫婦に聞いて理由がわかった。
「花を咲かせたら売れないんだよ」と、夫婦が口を揃えるように、食用は蕾のうちが花。開花すると味は落ちるわ、茎は固くなるわで、商品価値がなくなるのである。
だから、蕾が膨らみ始めたら、せっせと摘むのが日課だという。潮風の吹き抜ける畑で、手のひらにおさまるほどの寸法サイズに折り取って、背中の籠へ入れていく。家へ戻ると一束二百グラムずつにきっちり束ね、紙で巻いて、長さを切り揃える。菜の花のきっちりしたパッケージは、農家の夜なべ仕事に支えられているのだ。他の葉物野菜に比べて割高感があるのもいたしかたない。
菜の花忌薩摩の春は黄いろより 千恵子
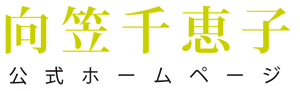

Leave your response!