俳句エッセー〔6〕 春いちばんの色なら、みかん色
町を歩けば「みかん」にぶつかる。東京・深川でのこと。江東区白河の深川江戸資料館を出てぶらぶらしていて、紀伊国屋文左衛門の墓を見つけた。近くにある清澄庭園は彼の別荘だったというから、少しも不思議はないのだが、紀伊国屋とわかったとたん、わたしの頭はみかんのことで一杯になってしまった。紀州生まれの文左衛門が特産のみかんを船に満載し、荒海を乗り切って江戸へ運んだという伝説を思い出したのだ。史実かどうかよくわからない話だが、江戸っ子には紀文の度胸のよさがしっかり刷り込まれている。
当時の紀州みかんは、ずいぶん小ぶりだったし、種もあったらしい。中国から伝わった原種に近いともいわれ、田道間守が伝えた橘の実がみかんの始まりという言い伝えがなんとなく納得できる。現代でも正月の鏡餅の飾り用などに、昔の品種がごく少量出回るようだ。また、鹿児島の桜島みかんも同種のものである。
いっぽう、遣唐使が鹿児島の長島へ伝えた温州みかんという系統もある。こちらは種がなく大粒なので食べやすく、みかんの主流になった。近代に入ると、早生や晩生の品種が開発され、近年はハウス栽培も盛んになるという具合で、みかんといえば温州みかんを指すようになっている。
温州みかんの早生種を代表する宮川早生と、九州の水郷・柳川で出合った。柳川藩の屋敷だった料亭旅館・御花を見学して土産品コーナーをのぞいたら、濃いみかん色をしたおいしそうなジュースが並んでいたのである。
ジュースは瓶入りで、お値段もなかなかのもの。説明書によると、明治時代の当主・立花寛治が農業による地域おこしを志して農園を開き、柳川で生み出された早生みかん・宮川早生を保護育成したそうだ。そのみかんが現代に至るまで立花家の農園で栽培され、ジュースとなっているのである。由来を知った以上は、ぜひとも飲んでみたい。ごくりとやると、濃くて、甘くて、酸味のほどがちょうどよい。その味に戦国時代以来の立花家四百年の歴史が重なるから、さらにおいしい。食べものは物語で彩られていっそう艶やかになるのである。
みかんは器に山盛りにしてこたつテーブルの上に置くものというイメージがある。たっぷりした量感が心をあたためてくれるのだ。もっとも、子どもたちにとっては、いいおもちゃが目の前にあるということなのだけれど。
有吉佐和子の小説『有田川』は、みかんに生涯を賭けた女性がヒロインだけに、川の氾濫に苦労しながらみかん栽培に奮闘する農家が描かれていて、読後は、あだおろそかにみかんを食べては罰があたると思ったものだ。その後、みかん産地を何カ所も取材し、現代もなおみかん農家の苦労が続いていることを知った。
白い花が咲き、黄色く色づいたみかん畑は、唱歌で歌われるとおりに美しくやさしい。たとえば、眼下に宇和海を望む愛媛県明浜町。真冬でも陽光がきらめき、濃緑の山にみかんの黄色が点々と広がる絶景の地で、石垣の整然した幾何美は世界遺産級である。
しかし、その畑をつくり、維持していくのは並大抵の労働ではない。みかんは温暖小雨、水はけと日当たりがよく、ミネラルを多く含む潮風の吹く土地を好むため、どの産地でも畑は海岸の傾斜地につくらざるをえないからだ。もっこで石をこつこつと運んで、段々畑を築くのである。
こうした海辺のみかん畑は各地にあるのだが、デコポンなど他の柑橘に転作されたり、放置されたままになっているところが少なくない。家庭からこたつが減ってみかんを食べる習慣が薄れたし、柑橘の種類が増えたうえ、輸入品の増加でみかんの消費量が激減しているのだ。
こんな状況を打破できる兆しもある。みかんの皮と牛乳を一緒に摂取すると花粉症の症状が緩和されるという研究が進んでいたり、養殖魚の餌にみかんの皮が用いられるようになっているのだ。愛媛では「みかん鯛」と呼ばれる。鯛が病気に強くなり、刺身にするとみかんがほんのり香る。
わたしは、旅行ではみかんを二、三個かばんに入れておき、車中で楽しむ。皮をむきつつ思い出すのは祖母のこと。母方の祖母はみかんを焼いて食べるのが好きで、皮をむいたみかんを小房に分けては長火鉢の網に並べ、ていねいに焼いていた。熱くなったみかんに炭の香がまとわりつき、おつな味になるのだ。みかんには思い出話がよく似合う。
長火鉢はさんで祖母と蜜柑かな 千縁子
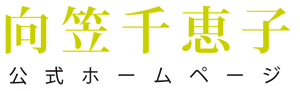

Leave your response!